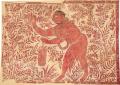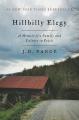最新日記
pherim㌠さんの日記
(Web全体に公開)
- 2025年
10月22日
12:38 -
よみめも105 火を産んだ更紗の航路
・メモは十冊ごと
・通読した本のみ扱う
・再読だいじ
※コミックは別腹にて。書評とか推薦でなく、バンコク移住後に始めた読書メモ置き場です。雑誌は特集記事通読のみで扱う場合あり(74より)。たまに部分読みや資料目的など非通読本の引用メモを番外で扱います。青灰字は主に引用部、末尾数字は引用元ページ数、()は(略)の意。
Amazon ウィッシュリスト:https://amzn.to/317mELV
1. 吉野弘 『現代詩入門』 青土社
小さな滝
かの女をはだかにするものを
あとからあとから身にまとうニンフ
なんとおまえのからだが
まるい荒い波のために熱狂することか。
やすみなくおまえは着がえをする、
かみの毛までかえてしまう。
そんなおびただしい遁走の背後で、おまえの生は
まのあたり清らに在りつづける。
この山崎栄治訳のリルケ詩(91-2)が堀口大學訳では、
水精といふは、着れば着るほど
あらはな肌ののぞくもの
それかあらぬかそなたの肉体
豊満な手荒な波に夢中になる。
絶えまなくそなたは衣裳をとり変へる、
髪の毛までもとり変へる、
この慌しい遁走のうしろにあって
そなたの生命は何時になっても純潔だ。
となる。(94) 「かの女をはだかにするものを あとからあとから身にまとう」と、「着れば着るほど あらはな肌ののぞくもの」との対照が、末尾の「まのあたり清らに在りつづける」と「何時になっても純潔だ」との時制の差を準備する。
盲人
――パリ
ごらん、彼が行く、都会を中断して。
暗い彼という地点の上で都会は消え去っている。
彼は行く、明るい陶器のおもてを暗いひびが走るのに似て。
そうして彼の顔の上には、ちょうど木の葉のおもてのように
まわりの物の反映が描かれている。
彼はそれを吸収してしまうことがない。
ただ彼の触覚だけが働き
世界をこまかな波として捉えようとするらしい。
静寂。一つの手ごたえ――。
そのとき彼は誰かを待ち受け選ぶ様子だ、
恭順の身ぶりで彼は手をあげ、ほとんど、
婚礼をする者のように荘重だ。 (高安国世氏訳)105-6
死体収容所
そこに並んで横たわっている彼らの様子を見ると、
互いを結び合わせ、この寒さとも
融和させるような何かの行為を
今からでも見つけなければ、と思っているふうだった。
そう、すべてはまだ終っていないかのようだ。
ポケットにどのような名前が一体
見つかるというのだろう? 彼らの口のまわりの
倦厭の表情を人は洗い落とそうとした。
それは落ちなかった。ただ純粋になるばかりであった。
ひげはしかし、幾分固くなってはいたが、
番人の好みに応じてきちんとそろえてある、
それはただ、物珍しげな参観人に嫌悪の念を起させないためだ。
目は彼らのまぶたの背後で
方向を逆にとり、今は内部を見つめていた。 (高安国世氏訳)107-8
――「物」をだまってさし出すこと。つまり「物」への愛情の告白でなく、説明でなく、存在そのものをさし示すこと。
(18・2・5高安国世記)
大人になって、自分の矢点だらけな実質に気付いたあとで、人に批評され否定されても耐えることは比較的たやすい。しかし、幼時期の「くらげなす漂える」ころに、たとえば一番身近な母親に嘲笑されたり、にべもない否定を受けたりすることは、ひどく怖しいことなのではないか。叱ることが、行為の末梢にではなく、子供の存在全体に刺さった場合は、自分を育定するゆとりをも子供に失わせてしまうのではないか。
私の考えだが、人間というものは救いがたいものであればあるほど、そのままそっくりを何者かによって肯定され愛されることが必要なのではないか。仕様がない失陥だらけのままを愛されてこそ、人は、その久陥に耐え、同時に他の人の矢点に対しても寛容になることができるのではあるまいか。それは、すべてが判ってしまった大人同士では純粋な意味では不可能であり、それが可能なのは、身二つになってからしばらくの間の母と子だけなのではないか。その時期の、子に対する母の盲愛は、子供にとって本当に深く必要なのではないか。
電車の中で、子供を叱らない若い母親を見て「それでいい」と思ったことを、敢えて説明すれば、そういうことになる。もちろん、それは後で考えて整理できたことであって、はじめはよく判らなかった。 159-160
吉野弘の新書『詩の楽しみ: 作詩教室』(よみめも99)のベースとなった本書ゆえ、読み味は一層深く発見も多い。子供心と詩心との近接をめぐる言及も読ませる。子供向け詩作コンクールの受賞作がまどみちお詩をほぼそのまま「剽窃」したものだったことへの作者まど本人の下記反応が良い。
「多分、そのお子さんは、私のその詩を気に入ってくれたんでしょう。子供は好きな詩を自分のものと思いこんでしまうようなことがありましてね。これまでにも、私の詩をうつして発表した子の例はあるのです。それを責めるのは、とても酷な感じがしますのでね。今度のことは、どうぞあまりお気になさいませんように……」 204
ここには「権利」の奴隷に成り下がった思考とは別の何かが働いているし、けれどそれを当たり前に働かせて在ることは、社会の外を生きる感覚の保持であり、できないというかやらない人間がほんとうに多いことは、考えてみると子供の頃から不思議に、不可解に感じていたことの一つかもしれない。
この世界、という恒常性感覚に亀裂を生じさせること。破綻をきたすこと。血は流されなければならない。そうして詩が訪れる。
下記は、マルグリット・デュラス原作 ジュールス・ダッシン監督作『夏の夜の10時30分』の台詞から。(235-6)
マリア お百姓さん
お百姓さん
麦の収穫はいかが?
ジュディス お百姓さん
お百姓さん
麦の収穫はいかが?
二人 どうか教えてくださいな
私にもしらせてくださいな
種をとって地面に撒く
種をとって地面に撒く
種を地面に撒いて
肥料をやって
お百姓さん
話しなさいな
雨がふらなかったら
どうするの?
雨なんか要らないの
雨なんか要らないの
お百姓さんの血があるもの
2. J.D.ヴァンス 『ヒルビリー・エレジー アメリカの繁栄から取り残された白人たち』 関根光宏,山田文訳 光文社
だがそれまで「掛け算」という言葉を聞いたことがなかったのは、けっして私のせいではない。学校ではまだ習っていなかった。家族がつきっきりで算数を教えてくれることもなかった。だが、学校でいい成績をとりたいと思っていた子どもにとっては、これは大きな挫折経験になった。未熟な頭には、「知能」と「知識」のちがいはわからなかったのだ。だから私は、自分は愚か者なのだと思いこんだ。 104
暗殺されない限り、米国大統領になるひとですね。という確信。現41歳のトランプ政権副大統領というレッテルに影響を受けた見方では見誤る。ラストベルトの白人貧困層、だけじゃないよね。トランプ政権入りって要するに、オハイオの没落地域出身で海兵隊経由イェール大学、って鬼展開を《神》展開へと昇華させるブースト要素の一つに過ぎなかった。
5日連続の厳しい面接会の最初におこなわれたこの日の会食から、私は、いままで自分たちのような人間には明かされてこなかったシステムの裏側を理解し始めた。
大学の就職課からは、自然な受け答えをして、面接官が「一緒に飛行機に乗ってもいい」と思うような人間として振る舞うよう、口をすっぱくして言われていた。それはそうだろう。実際、誰だって、気の合わない人と一緒に働くのはいやに決まっている。
だが、面接は就活生にとって、何よりも重要な機会だ。そんなふつうのことを、いまさら強調する必要があるのだろうかと感じたものだ。それだけでなく、面接では、成績や履歴書はそれほど重視されないとまで言われていたのである。つまり、イェールのロースクールという血統書のおかげで、私たちの片足は、すでにドアにかかっている。そのため、面接で試されるのは、社会性ということになる。会社に馴染めるか、重役会議でものおじしないか、将来のクライアントとよい関係が築けるか。面接官はそこを見ている。
だがじつは、一番難しいテストは、気づかないうちにすでに終わっていたのだ。 331
その下地には、いま表面的には対立構図を描く南部黒人層の、ミシシッピから徐々に北上してきた“地下鉄道”的情緒さえ共有し、もちろんアイビー・リーグの知的エリート層には彼らの力の源泉たるコネ的受容回路が確保され、カトリックの成人洗礼まで受けていて福音主義ともアンチ福音派とも距離はとるけど聖書に左手を置く説得力は半端ない。おまけに海兵隊出身でイラク駐兵経験ありっていう、パトリオティックな風潮が来た際のヴァンス政権は、確実に途轍もないことになる。
最大の強みは、これから背負っていく保守潮流の各軸に対して、最も批判的な視座をヴァンス自身が具えること。トランプは中ボスに過ぎなかった、ずっとヤバい奴がもう控えてる感。
ただ、私たちのコミュニティの3分の1の人が、明確な証拠があるにもかかわらず、大統領の出自を疑っているとするならば、ほかの陰謀説も、思ったより浸透している可能性が高いだろう。
これは自由至上主義のリバタリアンが、政府の方針に疑問を投げかけるというような、健全な民主主義のプロセスとはちがい、社会制度そのものに対する根強い不感である。しかも、この不感は、社会のなかでだんだんと勢いづいているのだ。
夜のニュース番組は倍用できない。政治家も言用できない。よい人生への入り口であるはずの大学も、私たちの不利になるように仕組まれている。仕事はない。何もじられず、社会に貢献することもできない。
社会心理学者は、集団で共有された念が、一人ひとりの行動に大きな影響を与えることをあきらかにしている。一生懸命働いて目標を達成することが、自分たちの利益になるという考えが集団内で共有されている場合、集団内の一人ひとりの作業効率は、ほかの条件はまったく同じで各自がぱらばらに働いたときよりも高くなる。理由は簡単だ。努力が実を結ぶとわかっていればがんばれるが、やってもいい結果に結びつかないと思っていれば、誰もやらない。
また同様に、何かに失敗したときにも、同じようなことが起こる。失敗の責任を自分以外の人に押しつけるようになるのだ。私はミドルタウンのバーで会った古い知り合いから、早起きするのがつらいから、最近仕事を辞めたと聞かされたことがある。その後、彼がフェイスブックに「オバマ・エコノミー」への不満と、自分の人生へのその影響について投稿したのを目にした。
オバマ・エコノミーが多くの人に影響を与えたことは否定しないが、彼がそのなかに含まれないことはあきらかだ。いまの状態は、彼自身の行動の結果である。生活を向上させたいのなら、よい選択をするしかない。だが、よい選択をするためには、自分自身に厳しい批判の目を向けざるをえない環境に身を置く必要がある。白人の労働者階層には、自分たちの問題を政府や社会のせいにする傾向が強く、しかもそれは日増しに強まっている。
現代の保守主義者(私もそのひとりだ)たちは、保守主義者のなかで最大の割合を占める層が抱える問題点に対処できていない、という現実がここにはある。 304
オハイオ~ケンタッキーの描写はけっこうアメリカ現代文学感あるし、イェール以降の法律事務所描写は法廷物ドラマを観ているよう。
文章は巧いし、それ以上に構成が練られてる。少なくともフォークナーとかヘミングウェイを読み込んで活かす巧緻は明確にあり、海兵隊までの荒れた少年期が描かれているようならこれ、大学以降の研鑽によって得られた技術になるから余計に怖い。加えてパートナーの“ウシャ”さんが聡明なインド系女性という、国内的にも対ユーラシア文脈でも2030年代以降の布陣が最強すぎて最凶。これで小泉進次郎より歳下なんだよ、勝ち目ない。
まぁそれはそれとして、口直しというかなんというか、しっとりアメリカ文学を読みたくなったな。
自分の過去を振り返り、生まれてから18年間に、自分自身でつくりあげた感情の引き金について、じっくり考えてみたことがある。すると、私は謝罪の言葉を信用していないことに気づいた。謝罪の言葉はいつも、こちらの警戒心を解くために利用されてきたからだ。10年以上前に、母が車で暴走したときも、その口から出た「私が悪かった」という言葉にだまされて車に乗ってしまったのだ。私は、自分が言葉を武器として使う理由がようやくわかってきた。子どものころ、周りの大人がみんなそうしていて、生き延びるためには私もそうせざるをえなかったからだ。意見が異なれば、闘うしかない。しかも、闘うからには、勝つしかない。
こうした教訓は、けっして一晩では消えない。心に葛藤を抱えた私は、不吉な統計の数値に圧倒されそうになりながらも、なんとか闘い続けた。ときには、その数字をじるほうが楽だと思うこともあった。悪事を働いて逮捕されるか、結婚しないまま4人の子どもの親になるほうが、私にとっては自然なことなのだと思おうとした。しかし他方で、家庭内のいざこざや、家族の崩壊も避けられないかもしれないと思うとつらかった。
精神状態が最悪なときには、逃げ場のない、自分のなかに昔から棲みつく悪魔と闘っても無駄であり、「それは青い目や茶色の髪と同じく、先祖から受け継いだおまえの一部なのだから」と思い込んでしまうこともあった。こうした過去の自分との闘いにはウシャの助けが不可久だったのだ。ひとりでいるときには、たとえ調子のいいときでも、感情の爆発を先送りにするのが精いっぱいだった。怒りを鎮めるには、テクニックと慎重さが必要なのだ。それは、私が自分をコントロールするすべを身につけただけでなく、ウシャが私の扱い方を知ったということでもあった。 357
3. 『インド更紗 世界をめぐる物語』 東京ステーションギャラリー
「インド更紗」が、ジャワ更紗やシャム更紗、江戸更紗やオランダ更紗と一点大きく異なるのは、それらすべての起源であることだ。これは「更紗」という語の付随しないインドネシアのバティックやアフリカ中部の絢爛な民族衣装まで広く言えることで、ヨーロッパ人主体の“大航海時代”よりも千年以上歴史をさかのぼる、インド洋の交易ネットワークが更紗伝播のベースとなった。このあたりについては過去にツイキャスで軽く浚ったことがある。↓
インド更紗とモンスーン貿易風
https://twitcasting.tv/pherim/movie/172737802
本書はこの秋11月まで開かれている同展覧会カタログで、上記ツイキャスでは喋っていない欧州と日本への伝播にフォーカスが当たるため、あまりにも極私的な観点としても更紗認識のバランス良い補完が叶う、絶好の機会となった。ので記事化も試みる流れが生じた。正式タイトルは《カルン・タカール・コレクション インド更紗 世界をめぐる物語》展で、カルン・タカール氏とはデリー出身で成人前にロンドンへ移民したコレクターで、メディア向け内覧会でも解説に立たれていた。話せるチャンスがあったのに、いま思うと臆してしまったのはもったいない。
特に良かったのは、
《白地人物草花文様更紗儀礼用布》17-18世紀(↑冒頭画像1枚目)
《白地立木形花樹文様更紗掛布(パランポア)》1740-50年頃
《白地人物文様更紗儀礼用布(マア)》1450-1650年頃
などと書き連ねてもほとんど意味がないとわかったので、記事URLを載せておく。(と書く現時点では未執筆だけど)
拙稿「」(近日URL追記)
ほかに、18世紀《白地聖母子文様儀礼用布》も興味深い。マリア更紗よ。
4. アゴタ・クリストフ 『第三の嘘』 堀茂樹訳 ハヤカワepi文庫
『悪童日記』(よみめも99)、『ふたりの証拠』(よみめも101)につづく三部作完結編で、ベルリンの壁崩壊後の世界が描かれる。原著は1991年刊行なので、ここは当時かなり注目されたポイントなのだろうけど、いま読むと前2作に比べ全体の抑揚が設定に引っ張られすぎ、小説的快楽の面ではかなり凡庸に堕した気はする。最もアゴタ・クリストフ作品をそういう翻訳版での読み味で評価するのは微妙というか、玄人の読み筋から遠いことは承知のうえで。
という流れから、三部作以降の作品が気になってきた。てか初期短編集成とか自伝とか、すでに色々邦訳出てるのね。いずれ読みたい。のいずれはいつ来るのか問題証明不能。
5. 逢坂冬馬 『ブレイクショットの軌跡』 早川書房
ビリヤードの最初の一擲であるブレイクショットが、アフリカで武装勢力が機銃を載せることからもわかるように、トヨタのランクルがモデルとわかる人気SUVの車名と重なり、様々な「この一閃」が波紋を起こしゆく群像エンタメ。サッカー青春BL物から金融ヘッジファンドや商材ビジネスが入り乱れる経済小説、中央アフリカの少年兵が主役となるアクション要素までがグローバル社会のもと一元化されそうでされないまま展開する。まぁ巧い。
でも直木賞とれなかった。ヤバすぎた『同志少女よ、敵を撃て』(次回よみめもで扱います)を落選させる賞ならそら仕方ないと思える部分があるものの、そんなに授与をもったいなさぶるものかね、とは思う。ふつうに色々うまくやってるんだから、淡々とあげてパイを分け合えばいいのにねぇ。(KONAMI
6. 石神賢介 『おどろきの「クルド人問題」』 新潮新書
「クルドの街・川口」へ、編集者の依頼で引っ越して取材に励むという企画物。
生まれから川口っ子で、しかも風俗街絶頂期の西川口とオートレース場を結ぶ道沿いで育った身から言えば、《修羅の国》度に変化はなくむしろ《住みやすい街全国1位》とかを誇ってた2010年代のほうがどうかしてた。
で。引っ越すといっても西川口のウィークリーマンションをちょっと借りただけっていうライトなやつで、取材先も赤芝新田っていう川口の古株住民でもほぼ初めて聞く市北部のめっちゃ限定された一区画がメインで、あとはそっち系の市議会議員や蕨の芝園団地や西川口のケバブ屋への取材をバランスよく取り揃えた体裁。なのでバランスは悪くないし、「クルド問題」とされる周辺の情報整理には良い。のわりに、一川口市民としては解像度というかピントがいまいち合わない消化不良感もまぁ残る。
とはいえ、本来の「クルド問題」がこの個別特殊な「クルド問題」の隠れ蓑になってる筋は明解に説明されているので、そういう理解水準から入るにはもってこいの一書。川口市が山手線内の面積にほぼ匹敵する、という一節はちょっと驚いた。ずっと鳩ヶ谷があったせいで、そういう見当識って働かない地元民きっと多い。続けるほどに地元マウントかましてまうな。
西川口なんかはさ、もっとインバウンド向けにも売り出せるぜって思うんよ。60万都市のくせに、そういう方向性はぜんぜん利かないんよね。SKIPシティを最後に、元そごうの使いかた含め再開発系すべて残念感が先立つ謎。
7. 井手川泰子 『絵本 火を産んだ母たち 女坑夫のおはなし』 さとこ虫・絵 或る書房
さいきん新版も出た井手川泰子『火を産んだ母たち』からの抜粋に挿画を載せた体裁。筑豊炭鉱の女坑夫らへの聞き書きにより描かれる世界は森崎和江『まっくら』(よみめも53)そのもので、ただし森崎固有の理知的にして燃え立つ筆致に比べ、女坑夫らの口調までも伝達しようという聞き書きならではの趣向にこだわる印象が強い。当該の『新・火を産んだ母たち』通読への助走として。
ところで森崎和江と石牟礼道子は1927年生まれで同い歳なのだと初めて知る。濃い交流があったことはどこかで読んだけど、生まれ年が同じというのは同志感もあったろうな。井手川泰子は1933年小倉生まれ。このあたりの人間関係の網目にも興味引かれる。
8. 高橋弘樹 『1秒でつかむ』 ダイヤモンド社
陶淵明の「飲酒二十首」を詳説しだしたり、この本自体がつかむ工夫に溢れており凡百のビジネス書とは異なる深趣。
・視聴者や消費者の皆さんは、そんなにヒマではありません。 139
・「設定がすべて」(見たことのない面白いものを描くためには、ストーリーに苦心するより)235
・「説明」ではなく、「体験」であるべき。(ストーリーを作るとき意識すること)367
だからこそ、「結果」を体験してもらうためには、「原因」も体験してもらう必要がある。
この場合であれば、
・妻と子どもが出て行ったあとも、そのままになっている娘の部屋
・そこには、娘と原宿に買いに行った何気ない人形が、まだある
・それだけでない、娘が小さい時、家族旅行で海に行って一緒に拾った貝殻が、瓶につめられたものも、勉強机にそのまま飾ってある
・リビングには、娘が小さい時くれた「お父さんありがとう」という手紙がある
こう描いてから、
・(離婚して、もう子どもと会えないんです)
ときたら、どうでしょう。
すみません。自分で書きながら泣きそうです。ぼくは。
会えなくなって悲しい、ということを描くなら、会えなくなる前の楽しい思い出を、主人公の頭だけでなく視聴者の頭の中にも共有してもらわなければ、この男のストーリーの喪失感を、一緒に体験することはできない。
つまり、ストーリーに「没入」できないんです。
この一炭入感】こそ、「ストーリー」を継続して観てもらう技術でもありますが、さらにそれを超越して、この章のテーマである「最後まで見て納得してもらう」ための、大切なポイントだと僕は、思います。 374-5
9. 高橋弘樹 『TVディレクターの演出術 物事の魅力を引き出す方法』 ちくま新書
《空から日本を見てみよう》を生んだ御仁と知って、一気に親しみと興味を覚えてしまった高橋弘樹なのですけど、『1秒でつかむ』と併せて読んでも、ここからどうReHacQへの展開が起きたのかはあまりわからない。TV地上波の枠組みでやってくことに意義を感じなくなったというのはまぁありそうだけど。
内容的には『1秒でつかむ』と被るネタも散見され、この本でなければというポイントはあまり見られず。個別に故人である夫の船の帰還を幻視してまう崖上マンションお婆さんの話とか切な良い。沖縄本島・北谷(ちゃたん)沖の「海底遺跡」ネタとか、そもそもいままでなぜ知らなかったのだという初出知識もあり。中城(なかぐすく)との近似性ね、そういうの好き。(本書言及はない)
10. 大野裕 工藤ぶち画 『マンガでわかる!うつの人が見ている世界』 文響社
序盤でうつ症状を「頭にかぶさる重たいお椀が締め付けてくる感じ」とする描写があり、この感じはよくわかるし低気圧時にも近く、しかしとすれば物理感覚そのものは悪いことばかりでないというか、締まった結果思考が一定のトーンに抑制される感じは時により穏やかで心地よさを覚えさえする。過感覚への言及もなるほどあるなと思わされ、それは周囲の人間が「頑張って」と言ってしまうことのリスクとして知られる《気遣いあるある》をめぐる下記言及にもじつは通底するのだと気づく。
「頑張れ」というのは「頑張ってほしい」という気持ちを伝える言葉です。そのため、事者は考えを押し付けられたような気持ちになってしまいます。周りの人は、当事者の気持ちを中心に考えることに意識を向けてみてください。 147
狭いサーキットを過剰に走ってしまうというか、視野狭窄下を必死にもがけばなお嵌る悪循環のごく一例として。
▽コミック・絵本
α. panpanya 『魚社会』 白泉社
デビュー作『蟹に誘われて』(よみめも45 魂消る)を2018年に読んだ際は、マニアックな寡作漫画家の印象を持ったけれど、知らない間に続々出していた。まぁほぼ年一ペースとしても、依然多作ではないだろうけど月刊誌連載一つで食べていけるくらいが質の安定を保証する圏域というものもたぶんあって、panpanyaはその好例では、など妄想する。実態は性別含め何も知らない。
魚市場と水産工場が魚人間にジャックされる表題作のほか、山崎パンの“カステラ風蒸しケーキ”を追い求める連続コラム漫画がたとえようもなくイイ。この良さはとても密やかなんだけど、ほのかな探検感に充ちているあたり穏やかな新鮮さを感じて味わい深い。
あとカバーを外した際の装丁が、すごくいいんだよね。たぶんデビュー作以来そこは統一されてそう。カバーの紙質が落ちてるのは、出版不況も関係してそうな。まぁちょっとこのひとの作品は揃えたくなるかな。何度も再読したくなる率高い。
旦那衆・姐御衆よりご支援の一冊、感謝。[→ https://amzn.to/317mELV ]
β. 李學仁/原作 王欣太/画 『蒼天航路』 6-31 講談社 [再読]
十数年ぶりに読む。序盤を飛ばしたのは、印象に濃いためと、そもそもあまり読み込むつもりなく描画の参考にと手に取ったのが6巻だっただけだからだが、延々読み継いでしまった。32巻以降は別の場所にしまったらしく、見つかったら読むだろう。
連載後半時にはリアタイで単行本を買い進める仕方で読んでいたけれど、李學仁/原作が比較的早い段階で李學仁/原案となり王欣太より文字サイズが小さくなったのは、単に方針転換なり仲違いなりして単独作者になったものと思っていた。いまwikipediaをみて、初めて李學仁が連載前半で死去していたことを知る。
2017年時点で1800万部発行というから、文庫版や極厚版をオリジナル単行本へ換算すれば1巻あたり50万部以上は売れていることになる。凄いことだけれど、そう考えるともっと売れても良い作品という気もする。連載完結まで丸11年かけた作品なのだから、毎年出せる小説とはやはり重みが違うのだし、けれどまぁごく同世代周辺の男子しか読んでない感じはあるから、こんなものかという気もする。
「その人物に与えるコマにおいては全員主役」という作者談通りの作品で、呉の描き込みが若干浅くはあるけれどひとつの小宇宙が成り立っていて、夷狄の作り込みもキャラへ収斂しちゃってるキングダムよりずっと多層的だし、晩年の荀彧や曹植の台頭による思想文学表現もガチで深い。これは今回あらためて感心した。華佗の医術を儒学文脈で曹操に対立させるとか、吉川三国志では記憶のかぎりあり得ない鋭さを感覚したけど、どうなんだろう。横光三国志含め読んだの中学生時だし、単にわかってなかったのかもしれない。
甘寧は相変わらずめっちゃ渋かったし、後ろ姿の劉馥とか仁王立ち死ぬ典韋とか懐かしくも新鮮に読む。この人生にあと何度もないのだろう楽しい再読時空でしたよ。
(▼以下はネカフェ/レンタル一気読みから)
γ. 芥見下々 『呪術廻戦』 28-30 集英社〈完結〉
28巻末、この頑ドメスティック物語にしては意外なるリアリスティック黒人さん来た。
29巻、五条悟再々来。伏黒恵のっとられby宿儺 vs 五条悟死体中の人乙骨優太っていう傀儡大戦になってきた。ナナミンのナタなそこそこ目立ってるのジワりゅ。
『劇場版 呪術廻戦 0』https://x.com/pherim/status/1614451311063478272
『呪術廻戦 第2期 懐玉・玉折/渋谷事変』https://x.com/pherim/status/1741210284298269016
30巻、完結。拙速感否めず。締めの回収モードはいいんだけど、なんだろう、たとえば釘崎甦らせるなら、もうちょっと琴線に触れるライン辿ろうよ、みたいな。パンダのその後エピソードは好き。
δ. 魚豊 『ようこそ!FACT(東京S区第二支部)へ』 1-4 小学館〈完結〉
陰謀説にハマる青年描写に、『チ。』との地平共有感が醸される特異性。むやみに跋扈するDSの作業場面を想像すると、ナンセンスギャグの不条理キャラっぽくて和む。
4巻は回収に終始するのだけど、第24話だけ外国舞台の独立話になっていて、本編とのつながりはよくわからないのだけど台詞なしの無差別銃撃描写がなかなか読ませる。
ε. 宮口幸治原作 鈴木マサカズ画 『ケーキの切れない非行少年たち』 1-2 新潮社
ケーキを3等分する切り方が思いつけない、少年院の境界知能少年少女たち。お涙頂戴にするのはNGだし、訴求するにも難しいラインを慎重にクリアする手つきは感心する。結果感情描写に漫画的な過剰さへの抑制も感じられ、とはいえ顔表情のみで記号的に完結させる怒気憎悪表現の画一性はやや気になる、というかもう少し何とかならないかなど思う。
ζ. 押川剛原作 鈴木マサカズ画 『「子供を殺してください」という親たち』 1 新潮社
1巻、予想以上に『ケーキの切れない非行少年たち』と同じ作品世界のムード内で、主人公押川がウシジマくん的に屹立しゆく展開。
今回は以上です。こんな面白い本が、そこに関心あるならこの本どうかね、などのお薦めありましたらご教示下さると嬉しいです。よろしくです~m(_ _)m
Amazon ウィッシュリスト: https://www.amazon.co.jp/gp/registry/wishlist/3J30O9O6RNE...
#よみめも一覧: https://goo.gl/VTXr8T