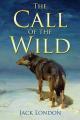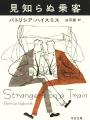最新日記
pherim㌠さんの日記
(Web全体に公開)
- 2025年
06月30日
17:36 -
よみめも103 海獣の呼び声 青春篇♡
・メモは十冊ごと
・通読した本のみ扱う
・再読だいじ
※書評とか推薦でなく、バンコク移住後に始めた読書メモ置き場です。雑誌は特集記事通読のみで扱う場合あり(74より)。たまに部分読みや資料目的など非通読本の引用メモを番外で扱います。青灰字は主に引用部、末尾数字は引用元ページ数、()は(略)の意。
Amazon ウィッシュリスト:https://amzn.to/317mELV
1. 入沢康夫 『アルボラーダ』 書肆山田
放心の午後
凍つた埠頭に黒い貨車が動いて行く
午後だ 幾千の光の途惑ひ
卓上の水仙の衰弱は
ぼくの左肩をも痺れさせる
「恋こそ棒にふったけれども……」と
低い声で話し始める勿体ぶった友には
いいかげんの相づちを打っておけばよい
午後だ
凍った埠頭の突端からの
目もあざやかな投身を
ぼくの揮発し始めた魂が企画してゐるといふことは
けだし
のろのろと動くあの貨車どもだけが理解するところだ
入沢康夫『詩の構造についての覚え書』が先月ちくま学芸文庫として再刊され、良い評判を複数目にして、かつ詩作課題を同人でちょうど企画していたこともあり、購入。正直、入沢康夫という存在自体これまで視野に入っておらず、吉増剛造本とか、岡田隆彦言及とかを通じてこの1,2ヶ月で急激に存在感を増した詩人のひとり。ほかに増したひととしては、広瀬大志とか。そのうち書く。
で、「構造」の本だった、たしかに。でも発見が幾つかあれど思ったほどではなくて、詩人はやはり詩なのかなと詩集に当たる。良い。
詩人はやはり詩なのだった。
(十三番目の……)
四月が残酷な月だと言つた人があるけれども 月といふ
月は程度の差こそあれ 残酷なところを持つてゐて たと
へば まつたくたとへばの話だが 五月は犬たちを発情さ
せ孕ませ 六月は麦藁帽の少女を沼に溺れさせる 七月は
瀝青を融かして家長たちの肌に引攣りを作り 八月は大口
開けてそれを笑ひ 九月は大アンテナの下でサーベルを無
意味に振り回し 十月はもう二度と逢ひたくない人を山の
あちら側から連れ戻し 十一月は水鶏の頸をひねり 十二
月は樫の門扉に罅割れを作り 一月は星々を砂丘の襞々に
撒き 二月はその星屑が搔き集められて恥づかしい疾病の
薬にされる
(月々はまた 慈悲深い一面も持ち たとへば またもや
たとへばだが 五月は少年たちに途方もない悪戯を思ひつ
かせ 六月は沼藻を蔓延らせて水魔の活動を抑制し 七月
は掃除ブラシを捨てて八月と取組み合ひの喧嘩をする 九
月は着弾点を故意にずらし 十月は泣き泣き海辺を歩き
十一月は聞こえる筈のない蒿雀の声に腹腸を千切り 十二
月は早起きして人の門出を送り 一月は夜空の麒麟に潤ん
だ眼を向け 二月は逆に頸を垂れてしきりに粥を啜る)
だが これらいづれもいささかならず平凡で意外に人間
化された十二の月を遥かに凌駕して残酷なのは 十三番目
の月 名無しの月 十三番目と仮に呼んだが これは十二
月の次に来るといふのではなく あたかも太陰暦に於ける
閏月のやうに 時の流れに割り込んでくる いな 閏月
とちがつて月の途中でも いつでも構はず割り込み居座つ
て五十日 百日 容易に去らうとはしない さういふ十三
番目の月 一切の形容語が失効する十三番目の月
さういふ人間の境域を絶した「月」を私は これまでに
何度か体験したやうに思ふ
けれども「筆舌に尽くせぬ」その「内側」その「実態」
そのほんの「欠片」なりとも 意味を持つた言葉にして
他人に伝へ得る日 そんな日が来るものだらうか 来るも
のだらうか 果して
吉本隆明とか石牟礼道子は、詩人でもあったということで。苦しいカナ。
2. ジャック・ロンドン 『荒野の呼び声』 海保眞夫訳 岩波文庫
Jack London "The Call of the Wild" Macmillan, US 1903
文明化されていた頃なら、彼は道徳的動機から、たとえばミラー判事の乗馬鞭を守るために自分の命を投げだしていただろう。したがって、もはや道徳的動機などにわずらわされずに行動し、しかも処罰を免れる能力を身につけたということは、バックの非文明化がすでに完了していることを示している。彼は好んで盗みを働いたわけではなく、単に胃の腑の要求にしたがったにすぎない。彼は公然とは強奪せず、棍棒と牙の掟を尊重して秘かに巧妙に盗んだ。要するに彼の盗みは、実行しないよりも実行するほうが容易だったので、実行に移されたのである。 37
バックはそれまで自分の生きてきた歳月、すなわち自分の物理的年齢よりもはるかに年をとっていた。彼は過去と現在とを結びつける存在だったのである。バックの背後には永遠の時が力強いリズムで鼓動しており、潮と季節がそのリズムにしたがって動くように、彼もまたそれにしたがって振動した。ジョン・ソーントンの焚火のかたわらに腰をおろしているバックは、広い胸幅をし、白い牙を持った、毛のふさふさした犬である。
だが、その背後には、あらゆる種類の犬や、犬とオオカミの雑種や、野生のオオカミなどの亡霊がひかえていて、バックを駆り立て、バックに指図する。バックの食べる肉を自分たちも味わい、彼の飲む水を自分たちも求める。彼とともに空気のにおいを嗅ぎ、いっしょに耳を傾け、野生の動物が森のなかで立てる物音を彼に教える。バックの気分を支配し、行動を指示する。バックが横になれば、自分たちもいっしょに横になって眠り、彼とともに夢を見る。そしてバックを超越して、自分たち自身が彼の夢に登場する。
これらの亡霊たちの命令は有無を言わせぬところがあったから、人間のことも、人間とのつながりも、日ごとにバックの心から遠ざかっていった。森の奥深くからひとつの呼び声が聞こえてくる。不可思議な魅力を持つその声を耳にするたびに、きまってバックは身震いを覚え、焚火とその周囲の踏み固められた地面に背をむけ、森のなかへ駆けこみ、奥へ奥へと突進したいという誘惑にかられる。なぜなのか、どこへゆくのかはわからないし、考えもしなかった。 110-1
バックの狡猾はオオカミそのものといってよく、野生動物の狡猾であった。彼の知性はセントバーナード犬とシェパード犬の知性である。それに、最も苛烈な学校で身につけた経験が加わって、バックは荒野を徘徊するいかなる動物にも劣らぬ恐るべき存在と化していた。獲物の肉のみを常食とする肉食獣として、彼は今やその生の絶頂期にあり、精気と活力に満ちあふれていた。ソーントンがバックの背中を手で愛撫すると、その手にそって一本一本の毛がパチパチ音を発した。閉じこめられていた磁気が手との接触によって放射されるのである。彼の身体のあらゆる部分、頭脳、胴体、神経組織のひとつひとつにいたるまで、すべてが絶妙に調律され、それらの部分のあいだには完璧な平衡が保たれている。目に映るものであれ、耳に聞こえる音であれ、とにかく行動を要するあらゆる事態にたいして、彼は稲妻のごとく反応した。ハスキー犬は攻撃においても防御においても素早く跳躍するが、バックは彼らの二倍も素早かった。ほかの犬がまだ視覚や聴覚を働かせているあいだに、彼はすでにつぎの行動に移っていた。すなわち、知覚と決断と行動を同時におこなってしまうのである。もちろん厳密には、まず知覚し、ついで決断し、最後に行動に移る。ただそれらの間隔がきわめて短いので、ほとんど同時に見えるのだ。彼の筋肉は活力にあふれており、鋼鉄のスプリングのように鋭くはじける。生命力が歓喜に満ち、奔流となって体内を走り、ついには彼の身体を引き裂いて、外界にほとばしり出るように思われた。
「あんな犬はこれまで見たことがなかったよ」と、ある日、ジョン・ソーントンはキャンプ地を悠然と出ていくバックを見守りながら、二人の仲間に話しかけた。
「バックが作り出されたあと、鋳型がこわれてしまったんだな」とピートが答える。
「まったくだ。おれもそう思うぜ」とハンズが相づちを打った。
三人はバックが悠然とキャンプ地を出ていくところをたしかに見たが、彼が人目のない森の奥深くに入った瞬間、恐るべき変貌をとげることは知らなかった。そのときのバックはもはや悠然とはしていない。直ちに野生の動物に変化し、ネコのごとくしのび歩く。暗がりに見え隠れする影も同然である。彼はあらゆる隠れ場を利用し、ヘビのように腹ばいになって進み、やはりヘビのように跳躍して打撃を与える。ライチョウの巣を襲い、寝ているウサギを殺し、一瞬の差で上に逃げ遅れたシマリスを空中で噛む。氷結していない水たまりの魚は容易に捕えることができる。ダムを補修しているビーバーがいかに用心深くても、バックの素早さのまえでは敵ではない。 140-2
3. ハン・ガン 『そっと 静かに』 古川綾子訳 KUON
한강 《가만가만 부르는 노래》 2007
十年ほど前に書いた短編小説で、死ぬ前に三時間与えられるしたら、太陽の光を浴びる時間に使いたいと書いたことがあった。今もその気持ちに変わりはない。その三時間のあいだ、陽光の中に全身を浸すのだ。ただし、愛するあなたと一緒に。私のいない長い時間を生きてくであろう、あなたの手を握って。 150
歌や歌詞をめぐるエッセイ集。ハン・ガン自ら作曲/作詩の曲をめぐる章もあり、原著では自ら歌ったCDも付いているらしい。
ハン・ガン自作朗読/歌唱等 https://han-kang.net/Sound
物書き中毒に近かった十年間の習慣を封印してしまうと、恐ろしいほどの虚無感に襲われた。子どもがおむつも取れていない、まだ言葉もうまく話せない時期でなかったら、私はもっと暗い場所へと押し流されていたかもしれない。子どもがいたから笑えたし、ふざけることができたし、愛することができた。いや、愛さなければならなかった。
その年の秋、ある夕暮れ時。オーディオにビートルズのCDを入れると、この歌をかけた。最初に家中の二重窓をすべて閉めてから、最大限までボリュームを上げた。どの部屋にも陰ができないように、灯りという灯りをすべてつけた。すると家は港を旅立つ船のように、非現実的な空間になった。よく滑るように靴下をはくと、フィギュアスケートの選手のように床を滑りながら踊りはじめた。どんなダンスでもない、ただ自然と踊り出すダンス。敢えて名前をつけるなら、ぴょんぴょん、ぴょこぴょこダンス? 子どもがはしゃいで私と一緒に飛び跳ね、私と一緒に床を滑った。互いの背中を押して、遠くまで滑った。「レットイットビー」のくだりになるたびに、すーっと床を滑って走る気分といったら!
曲に合わせて声の限りに歌いながらたまに泣いたりもしたけれど、母親が泣いているのか 笑っているのかわからなくなるほどこの状況に興奮した子どもは、その場でジャンプを続けた。いま思えば下の階の住民には申し訳なかったけれど、そのときは狂気にでも囚われていたのかなにも考えられなかった。華やかなシンセサイザーの間奏が入るたびに、狂ったようにくるくるとその場で回りながら目を閉じた。その一つ一つの音が光のようだと、生の光のようだと感じた。閉じた目に押し寄せてくる光、祝福、喜び、そのすべてだと。そう思いながら涙をふいて、またふいて、しまいにはわんわん声を上げて泣いた。あんなに大きな泣き声も、跡形もなく飲み込んでしまう音楽の中で。
それから子どもはヘイピーしよう、ヘイピーとねだるようになった。オートリバースでひた すら繰り返された「レットイットビー」という言葉を覚えたのだった。いつもそこに憂鬱がとぐろをまいていた時期だったから、二重窓をすべて閉めて音楽をかけると、ダンスと涙は必ず私を救いにやってきた。おそらく子どもも一緒になって救ってくれたのだろう。もちろん、下住民にとっては災難だっただろうが……。 56-7
訳者あとがきによれば「書きたいのに、書かなければいけないのに、書けなかった」時期の言葉たちで、ハン・ガン自身にとって「大切な作品」との由。エッセイ部にはその苦しさが漏れ出る箇所も多く、元来の文章力も健在で読ませるが、歌詞の訳という難しさゆえか、詩のパートは総じてあまりぱっとせず、心に来るものが少なく、ハン・ガンらしからぬ平板さすら覚えてしまう。これはリズムとか韻とかが削ぎ落とされた意味主体で(おそらく)訳す方針ゆえかとも思われ、といって訳者が気張りすぎても鼻につく(たとえば若い頃の池澤夏樹によるケルアック訳などのように)だけだろうから、なかなかに難しい。ハングルくらい覚えて原著に当たれ、というのはあるかもしれない。
(155-6 路上で泣く女 メモ)
あの夢はなにを伝えるために私のもとを訪れたのだろうか。ユングが分析したように、無意識からのメッセージだとしたら、私よりたくさんのことを知っている「私」は、どんなメッセージを伝えたかったのだろう。
あの夢を見た、私は長いこと体調がすぐれなくて、疲れ果てていて、日に日にすさんでいった。嘘しか言えなくて、いっそのこと永遠に口を閉ざしてしまいたかった。
美しさがなによりも必要な瞬間とは、そんなふうにちっとも美しくない瞬間だということなのか。夢がなによりも必要な瞬間とは、一時も熟睡できないくらい肉体も魂もぼろぼろになっていたあの刹那だというのか。これ以上ないくらい不幸な時間、あらゆる美に唾を吐きかけて踏みつぶす時間。自らを憎んで目を背ける時間。獣の時間、堕落の時間に、あの切々とした笛の音は、どんなふうに漆黒の海に響くのだろう。
それはもしかすると、マフムドが追求していた世界と重なる部分もあるのかもしれない。暴力と苦痛という現実の中で彼が自分だけの世界を淋しく迎え入れていたように、私も心を手放してはならないということなのか。あの笛の音を忘れずに、あの瞬間の震えを掌に刻んで、進むべきだということなのか。死者の魂に届くほどの切実さで。黒いコートを纏った男に言い返した自分の言葉のとおりに、「それがすべて」だという淡々とした静かな気持ちで……。 172
4. 吉田修一 『国宝 上 青春篇』 朝日新聞出版
まぁすごい。吉田修一、『パレード』とか初期に幾らか読んで巧いし不穏さもあるし、エンタメ寄り純文学系作家としてのしてくんだろうなくらいには予想も期待もできたけれど、エンタメ極振り路線に振ったうえこの到達点は想像の遥かに斜め上だしってかこのですます調は心底すげえ。
映画化も知らずに読んでいたほどなので、ネット上に散乱するのだろう付帯情報も一切触れてないのだけれど、いったいどういう経路で本作を書くにいたり、どれだけ取材や下準備を重ねたのか、けっこう気になる。なんというか単なる想像の域には収まりようのないリアルの手触りをそこかしこに感じざるを得ず、そう数々の堕落出奔色恋エピソード群の逐一に、そして舞台周りのアクシデントの一つ一つに。
映画『国宝』 https://x.com/pherim/status/1932635647082414139
小説冒頭部の長崎での旅館カチコミ場面、映画ではヤクザ組長に永瀬正敏が扮してもう堪らん名演かまし、吉田原作の沸騰が余すところなく再現されおり深甚。吉田修一小説の上記「不穏さ」の由来たる暴力性を、映画的アクション過剰演出をむしろ抑えた質実な立ち回りで魅せる試み、大変良かった。
5. 朝比奈秋 『サンショウウオの四十九日』 新潮社
最高度に多くの臓器や身体部位を共有する結合双生児の姉妹を主人公とする本作、思考や感情の共有と遮断、感覚の乖離などの描写が各々秀逸だし独創的で読ませる。実父も三つ子だがひとりだけ一番最後に健康体で生まれ落ち、その健康はしかし伯父や叔父を吸収した結果という筋もうまく語る感じは萩尾望都『半神』も想起させ、これら全体がエマヌエーレ・コッチャ『メタモルフォーゼ』を思わせる。
結局のところ、私を震えあがらせたものは私たち特有のものではなかった。私と瞬の関係は父や母や友人らのそれと何の変わりもなかった。パート先の常連客の言葉に傷ついて母の胃に潰瘍ができたり、泉が彼氏の言葉に耳を真っ赤にしたりするのを見ればわかる。自分だけの体を持っている人はいない。みんな気がついていないだけで、みんなくっついて、みんなこんがらがっている。自分だけの体、自分だけの思考、自分だけの記憶、自分だけの感情なんてものは実のところ誰にも存在しない。いろんなものを共有しあっていて、独占できるものなどひとつもない。他の人たちと違うのは、私と瞬はあまりに直接的、という点だけだった。自分たちが特別でないと認めると、サンショウウオは物音を立てずに通り過ぎていった。
そういった事実は思春期まっただ中で、自分らしさを求める自意識過剰な私には辛かった。この体では、自分だけの個性を保つことは難しかった。そして、それがどうしようもない事実だとわかると私はすごく投げやりになった。そこから何でもオーケー、全てがどうでもよくなった。それまでは高校を卒業してからの進路で瞬とよく話し合った。絵を描きに芸術学部へ行くか、美容の専門学校へ行くか、どちらへ進むかがいつも議題だった。しかし、それもどうでもよくなって、娘たちの将来を案じて母が勧めた看護学部にすんなり進学することにしたのもそういったことからだった。 88-9
手塚治虫でもできなかった小説だからこそ可能な表現を淡々とそして次々にやってのけている観もあり、飽きない。と感じさせる、医師作家ゆえの要素もきっと強いんだろうな。個別の表現レベルで逐一意識化されたりはしなかったけど。
本作をめぐる巷の評価や議論など全く不知なのだけど、同じ芥川賞を一年前に受賞した市川沙央『ハンチバック』との当事者性の違いをめぐる当然あったろう議論は、とくに両作の締め方に関連してすこし気になる。どちらもわざわざ締めにかかってる印象がつよく、この方法は芥川賞レースに適応したもので作品世界本来の要請に従属はしてない感じがあるんだよね。どうなんだろう。
などと書いたあと画像検索↓したら、巷の評価以前に新潮公式サイトでまず市川沙央による書評が載り『半神』への言及があり、次に萩尾望都x朝比奈秋が配置されていて、担当編集者先回りすぎでは、なと一年遅れの感慨に耽るなど。→https://www.shinchosha.co.jp/book/355731/
6. フィリップ・K・ディック 『高い城の男』 浅倉久志訳 ハヤカワ文庫
リドスコ製作の配信ドラマ版イメージが鮮烈すぎて、原作を読もうという気になかなかならずだったが、予想外に色々違って楽しめた。そもドラマ版の鍵となるフィルムがここでは小説であったのも知らなかったくらいで、なかでも田上の存在感が主人公級なのには驚いた。そしてその登場場面が、すべてドラマ版で演じたCary-Hiroyuki Tagawaの風貌で脳内再生されてしまい、B級感醸されつづけ困った。本人に罪はないのだけど。
まぁこの改変はでも、ルーファス・シーウェル演じるナチス将校一家がクローズアップされるのも込みで、今なら即批判を浴びるやつだろう。2015年放映開始作でこの違いは、時代変化の素早さ感じざるをえず。てかあまり指摘されないけど、このPC圧力強化ってコロナ禍と明らかに関係してますよね。「わたし傷ついた」的お気持ち至上主義のポリコレ棒で人を叩くのは正義みたいなやつ。
フィリップ・K・ディック、アシモフとか純粋SF系作家を代表するひとりってイメージ持ってきたけど、SF的想像力で設定された舞台を背景とするハードボイルドがやりたいひとなんかなー、と印象の輪郭が徐々にくっきりしてきたなう。合ってるのかは知らず。
7. 一穂ミチ 『ツミデミック』 光文社
とても新鮮。たとえばネットの匿名掲示板で集まった自殺志願者グループの一話とか、話の枠組み自体は既視感満載だけど細部がいちいち新しいというか。自殺したと思われていた少女が、実は厳格な母から逃げたくて自殺を演出したうえ愛人とかお水関係で生き延びてるという話も、単に新しいのでなく馴染みを感じさせながら、でも読んだことない角度を切り開いていくモードが穏やかなワクワク感を催すというか。
総体として、切り口の新しい気鋭の若手という形容では違和感醸す種のすでに研鑽を経た文体という印象を抱いて、しかし著者名に記憶はないのが不思議だなと思ったら、BLとかのジャンル小説で分厚い履歴のあるひとだったのね。こういう書き手は一般のエンタメとか純文学方面へ乗り出してくるのは確実に地力溢れてのことなので、今後も読むのが楽しみな作家が増えた観。高村薫とか桐野夏生みたいな展開がBLからも起こるというのは、理路としてならそも頷ける話ですわね。あとは誰がその先鞭をつけるのかっていう。
8. 村上春樹 『1973年のピンボール』 講談社文庫
女は眠るように目を閉じ鼠にもたれかかっていた。鼠は肩から脇腹にかけて、彼女の体の重みをずっしりと感じる。それは不思議な重みだった。男を愛し、子供を産み、年老いて死んでいく一個の存在の持つ重みであった。鼠は片手で煙草の箱を取り、火を点けた。時折海からの風が眼下の斜面を上り、松林の針の葉を揺らせる。女は本当に眠ったのかもしれない。鼠は女の頬に手をあて、一本の指で薄い彼女の唇に触れた。そして湿っぽく熱い彼女の息を感じる。
霊園は墓地というよりは、まるで見捨てられた町のように見える。敷地の半分以上は空地だった。そこに収まる予定の人々はまだ生きていたからだ。彼らは時折、日曜の午後に家族を連れて自分の眠る場所を確かめにやってきた。そして高台から墓地を眺め、うん、これなら見晴しも良い、季節の花々も揃っている、空気だっていい、芝生もよく手入れされてる、スプリンクラーまである、供え物を狙う野良犬もいない。それに、と彼らは思う、なにより明るくて健康的なのがいい、と。そんな具合に彼らは満足し、ベンチで弁当を食べ、またあわただしい日々の営みの中に戻っていった。 84
9. 円城塔 『リスを実装する: A squirrel, animated.』 Kindle
新たに就いた職種をAI自動化により奪われまた次の職種へと移り続ける労働者男が、リスAIプログラムの実装過程にみるミクロ創世記的夢想のような短編小説。そいつの生きる世界を設えている俺こそ設えられた世界を生きているという俯瞰心象により読み手を巻き込む設えの巧緻。
初期お掃除ロボットの中に、育ち盛りの息子にみるような親近感を、進化しゆくお掃除AIに巣立ちゆく息子へ抱くような切なさを抱く一節が妙に尾を引く。
10. オザワミカ編 『BOOKMARK 09号 顔が好き♡』 @bookmarkFB
金原瑞人らが発行するフリーブックレットの第9号(よみめも71で15号を扱ったシリーズ)で、装幀特集。「顔が好き」の顔とはつまり表紙デザインのこと。選ばれた装丁の担当装丁家十数人が、各々の自作解説的エッセイを付記する。
川名潤による冒頭見開きの文章がとても良いので、以下全文引用する。
翻訳もの装丁の手順とスクラロース
川名潤
原稿を読んで手がかりを探してそれを図像化し、パッケージの顔をつくることに変わりはないのだが、翻訳ものの小説の装丁となると、少し手順が増える。まずその作家の生まれた国について調べる。インターネットで風景写真を見たり、その国で出版されている本の装丁を見たり、その国の音楽を聴く。パスポートを持たず、本州から出たことさえない(北は福島、西は兵庫まで)私は、どうにかその作家がその話を書かなければならなかった空気に触ろうとする。次にA4サイズの紙を用意する。 その話を読みはじめ、主人公の名前を中心に書く。場合によっては棒人間に毛が生えた程度の人相を描く。次のページに出てきた人物の名前を書き、そこに向かって線を引き、「ルームメイト」やら「恋人」やらと添える。乗っている車、持っている靴の特徴を書き、他人から見れば歪な四角形にしか見えない程度だがその形を描く。周辺に向かって高密度に広がっていく相関図。しかしそれは完成したためしがない。聞き慣れない名前を覚えるのが苦手なのでそういう作業をするのだが、大抵の場合、途中で手がかりが見つかるからだ。ある人物が口ずさんだ歌のフレーズ、ふとした動作によって舞った埃、脱いだシャツの袖のほつれが装丁のイメージとなる。
気取った言い方にすると以上。つまり物覚えが悪く、海外の人々の名前や地名を、読んだ端からきれいに忘れていくので、私にとって翻訳ものの装丁はちょっと面倒だ。
しかしその面倒さが実は大切で、事務所でカップラーメンをすすり、ゼロカロリーのコーラをチビチビやりながら日本語の活字を組んだりしているジャンクな日常から遠く離れ、生まれてこの方、乗ったことのない船に乗るためには欠かせない作業なのである。ほつれるのはジャージの袖であってはいけない。口ずさむのがアニソンであってはいけない。埃はミストラルの冷たい風に乗って地中海に舞い降りなければいけないのだ。結果、私の場合は、手がけた装丁がおそらく過剰に「翻訳ものの顔」になっている気がする。そこそこに気取った顔をしているのだ。そうなるように心がけている。私はそれでよしとしている。もちろん、商業的にはカジュアルであることが、クライアントである出版社には歓迎されたりもするのだが、私としてものを読みたいと思う時は、たとえ徒歩2分のコンビニで買ってきたカップラーメンを食べながらであっても、「来月こそはパスポートを取って、さっきのページで死体が逆さに突っ込まれたモルなんとか街の煙突でも見てみたいなぁ。あ、旅行用の革靴とジャケットを買おう。その前に出過ぎた腹をひっこめるか。明日もコークはゼロカロリーだ」とかなんとか考えていたりするからだ。 4-5
▽非通読本
0. 青木淳悟 「旅行(以前)記」 (西崎憲編《短文》集『夕暮れの草の冠』収録) 柏書房
海外旅行未経験の母をハワイへ連れていこうという中年男の手記。父を亡くし独り身となった母を気遣いハワイへ連れて行こうと目論むのだが、なにせ語り手自身が三十過ぎでの人生初の渡航先がハワイで海外経験に乏しく、クレジットカードを持ったことがなくJTB発行のクレカもどきプリペイドカードで凌ごうという謎努力に尽力する奴なので、旅行準備もままならない、という話。青木淳悟の実録エッセイとも読めるが、青木淳悟なので大変怪しい(私見)。
北朝鮮のミサイル試射報道でハワイ行きを危ぶんだり、実母に40年ぶりの水着を買わせたり、ホットコーヒーを注文できずハッカフィと発音すれば良いと発見したり、具体記述は個別にそこそこ面白い。ただ耽溺したいタイプの読み味ではなく、それなりに意外な展開はあれどそこから湧く感興もそこそこに留まり、やみつき感とかもっと読みたい感じとかは生じず。でも下手さを感じる箇所もない不思議。
▽コミック・絵本
α. 鶴田謙二 『空は世界のひとつ屋根』 1 白泉社
南硫黄島よりさらに南に浮かぶ奥の鳥島へ空港管制官として赴任する青年目線でみる、島のけったいな人々観察録。南すぎて日本国内から移動できずグアム経由っていうのがリアルで、マリアナ諸島北端という設定も興味深い。てか沖ノ鳥島が小笠原諸島とは別の海嶺上なの初めて知った。
水着女子メインの健康的エロ描画は健在ながら、いつもの冒険SF的想像力が出番なくリアル詳細設定が楽しめるのは、鶴田作中けっこうレアかも。
あとがきも興味深くて、本作はアナログからデジタルへ移行した初期の作品で、「マンガ」で常識感覚となっているペン画+モノクロのイメージは描く側も読む側もデジタル移行する以上過去のものになる、という前提に立って鉛筆描線の上に色を塗るようなことを意識的にやっていて、結果飛行機描写が多いのもあって部分的に宮崎駿マンガ&絵コンテみたいに
旦那衆・姐御衆よりご支援の一冊、感謝。[→ https://amzn.to/317mELV ]
β. 五十嵐大介 『海獣の子供』 1-5 小学館 [再読]
突如再読の要を感じ、まとめて読む。前半は初読の印象をなぞる読み味だったが、後半は記憶も薄れ新鮮に展開を楽しめた。結果初読時は未読だったろう五十嵐『魔女』『ディザインズ』との近接を感覚、あと『鉄コン筋クリート』のシロクロ海洋オマージュ感も強く催した。
なんにせよ、海の果てで人知れず為されゆく世界更新、こそがリアルでヒト社会の事どもなど幻、みたいな銀河感覚は良いよね。
γ. 瀬野反人 『ヘテロゲニア リンギスティコ ~異種族言語学入門~』 6 KADOKAWA
着想が毎度面白いし、ここから“Arrived”的壮大さへ展開しゆく想像力の萌芽をみてる感がある。とはいえ6巻中盤からの展開は、不思議とヤギのうるささが生理的にくるものあり、ススキがダウンして醸される不安に引きずられるのと相俟ってやや読みづらい。それ自体が新鮮な読み味ゆえトータルで良展開とも言えるかもだけど、このテンションをやたらくり返されたらやだなという新たな不安もこれを書くうち催されてきた。
旦那衆・姐御衆よりご支援の一冊、感謝。[→ https://amzn.to/317mELV ]
(▼以下はネカフェ/レンタル一気読みから)
δ. 山口つばさ 『ブルーピリオド』 11-6 講談社
11巻、市民向け絵画教室での屈託。講師が高校生時に世話になった恩師である点、かくかくしかじかを想わせる。藝大に入るとかつての帰属集団から相対的に声をかけられがち、かつ入学後自身を見失いがちなので原点回帰を志向しがち、みたいな導因はたぶんある。
12巻、パープルーム的共同生活コレクティヴ。主が天然才知美女な改変がブルーピリオド的よな。にしても主人公が油画1年の時点でこれもってきちゃうの面白い。そもそも藝大受験物語だと思ってた余波もあるだろうけど、この先どうするのかほんと読めない。
13巻まさかの閉鎖、カオスラウンジでしたっていう。そして真田さん「殺された」END。切りかたうますぎのけぞる。
14巻、貸画廊個展&コンクール応募編。に死が絡むサスペンス構成、明らかに巧くなってるよね。
15巻、他殺でも自殺でもない真田さんの死を軸に回った夏休み編END。藝大生の自死問題へ突貫するのかと期待もあったのでやや膝がっくん感もあり。
ε. 龍幸伸 『ダンダダン』 1,2 集英社
さきにみたアニメ版は、怒涛の激速展開で意味がわからないまま面白い、意味がわかることの必要性を感じない楽しさがあったけれど、漫画原作はさすがに意味がしっかりわかって別の面白さあり。とはいえ読み継げるほどの楽しさが主観的にあるかは、1巻時点ではまだ未知数。
で、2巻。面白いといえば面白いんだけど、ネタの掘り込みが思いのほか浅く、これなら思い切り犠牲を払ったアニメ版のテンポ優先志向は正解だったな、って感想深まる。
今回は以上です。こんな面白い本が、そこに関心あるならこの本どうかね、などのお薦めありましたらご教示下さると嬉しいです。よろしくです~m(_ _)m
Amazon ウィッシュリスト: https://www.amazon.co.jp/gp/registry/wishlist/3J30O9O6RNE...
#よみめも一覧: https://goo.gl/VTXr8T